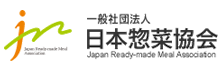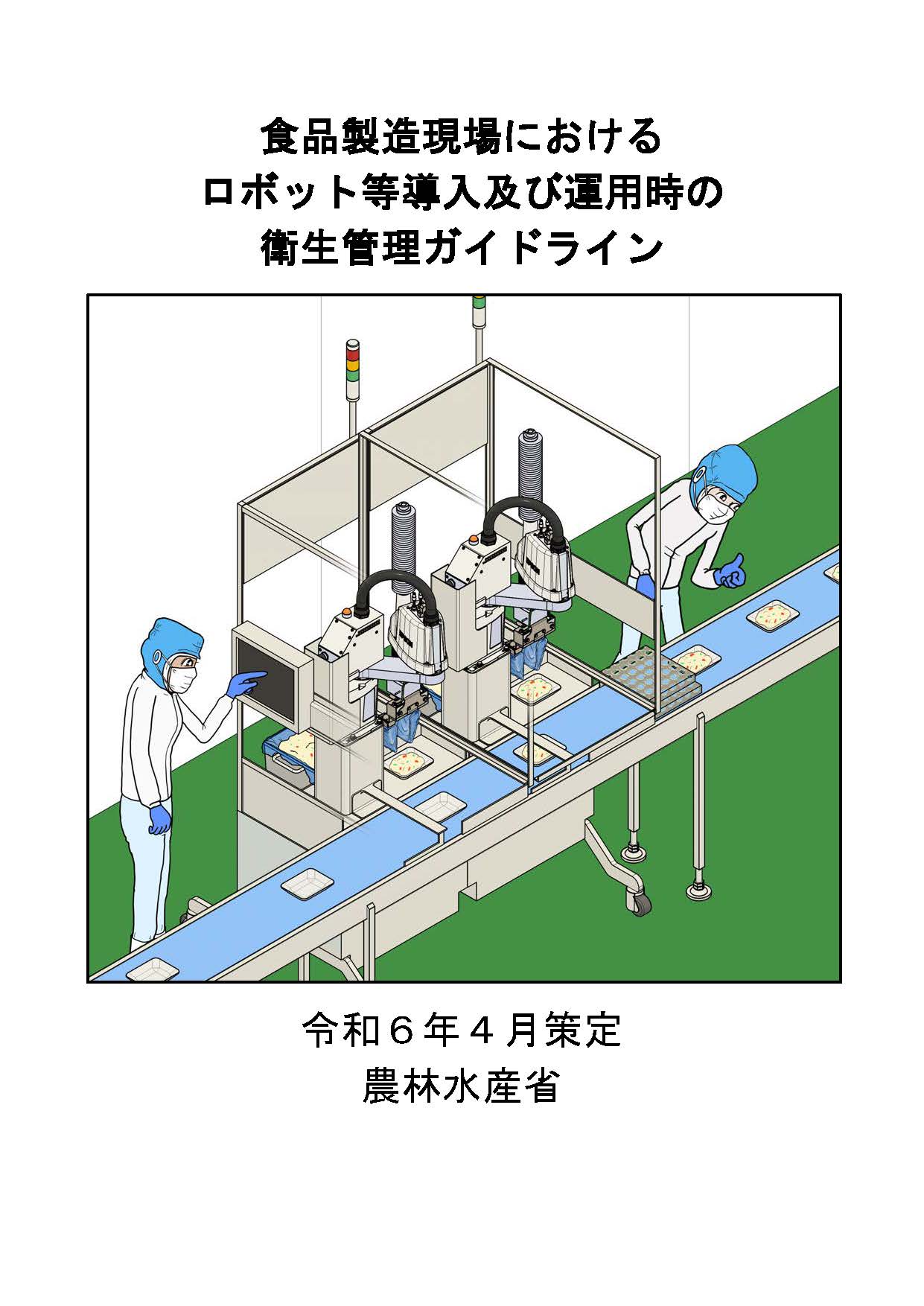近年、食品工場及び業務用厨房施設等において液化石油ガス及び都市ガス(以下「ガス」という。)の消費設備による一酸化炭素(以下「CO」という。)中毒事故が発生しています。
特に昨年8月には、静岡県の企業において、社員食堂の厨房で業務用食器洗浄機の使用中に従業員11名がCO中毒となる事故が発生するなど、2022年は3件(死者0名、CO中毒16名)の事故が発生しています。これらの事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。
食品工場及び業務用厨房施設等においてひとたびCO中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、換気、点検、手入れ、業務用換気警報器設置等の重要性について、業務用厨房等の所有者や使用者等の理解を促すことが重要です。
経済産業省は、食品工場及び業務用厨房施設等におけるガスの消費設備によるCO中毒事故を防止するため、下記の事項について、ガスの消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起をします。
記
1.ガスの消費設備の使用中は必ず換気(給気及び排気の両方)を行うこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切りの状態にすることが想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行われているか、必ず確認すること。なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。
2.ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時にガスの消費設備及び換気設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。
3.ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用すると共に、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行うこと。特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。
4.排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。
5.万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。
6.ガスの消費設備及び換気設備の正しい使用方法及び換気の重要性について、調理に従事する従業員(パート・アルバイト等を含む。)への教育及び周知を実施すること。
通知文書